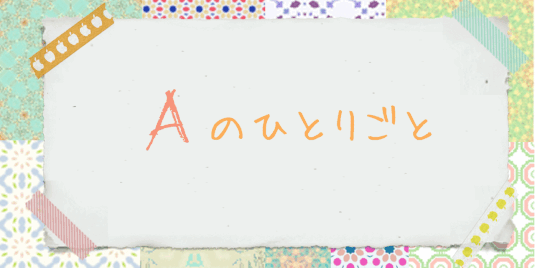
久しぶりの更新
ブログを書くのが久しぶりすぎて、更新の仕方がわからなくなり焦りました。さぼりすぎですね‥‥‥
ホームページやSNSではお知らせさせていただいているので、ご覧いただいている方もいらっしゃると思いますが、昨年に3冊目のエッセイを出すことができました~
『海外児童文学をめぐる冒険』は、ずっと自分の中でどこかで表現したいと思っていたことがテーマだったのですが、まさかこのような形で本にしていただけるとは思わず、本当に驚きと喜びとありがたい気持ちでいっぱいです。
この本の中では、わたしがこれまでどうやって絵本や物語を読んできたかなどを書いています。
その中でも大きなテーマのひとつとして、大好きで大尊敬する吉田新一先生からうけとったものを、なんとか欠片でも記録しておきたいというのがありました。吉田先生と出会えたことは、ほんとうにわたしの読書人生をかなり豊かにしてくれたと思っているからです。
本を書く前に吉田先生にお会いして「こういう本を書きたいと思っているのですが‥‥」ということを説明し、許諾していただいたということもあり、公開ファンレターを書くような気持ちも少なからずありました。
私の文章力では表現しきれなかった部分もたくさんあるのですが、「読書のよろこび」を手渡してもらえたという経験を書き留めておきたかったのです。
『いのちの木のあるところ』読書会に参加してきました!

11月の1冊は『いのちの木のあるところ』(新藤悦子 著/佐竹美保 絵/福音館書店)でした。
今回はなんとスペシャルゲストとして、この本の著者である新藤悦子さんが参加してくださいました。おかげで、2023年度最後を締めくくるにふさわしい贅沢な会になりました(12月の読書会はお休みです)。
どんな会になったのか、ざっくりではありますがレポートいたしますね。
『いのちの木のあるところ』
物語の舞台は13世紀のトルコ。主人公のトゥラーンを中心に、テンポよく物語は進みます。個性豊かな登場人物と共に、トルコの風土・文化に建築様式や世界情勢など多彩な魅力にあふれる1冊。
最近の児童書では珍しい重量級の部類に入る存在感ですが、ひとたび読みはじめると一気に読めてしまう人も多いのでは。見慣れない名前や名称にひっかからなければ、ぐいぐい読みすすめられる面白さだと思います!
最近、嬉しかったおはなし
信濃毎日新聞で連載中の『本の宝箱』ご覧になっていただけているでしょうか?
新聞の紙面はもちろん、新聞掲載から数日後にデジタルサイトにもアップされるようになり、遠方の方にもご覧いただけるようになりましたので、ぜひそちらもご利用ください。もうすぐ、連載も1年になります(早い!!!)。最近は、連載の掲載日当日に紹介を見て本を買いに来て下さるお客さまもいらっしゃって、とっても嬉しいです。ちょっとした感想を教えていただけるだけでも、とても励みになります!
朝日小学生新聞『パンダのポンポン』

今更のご報告ですが……本年度も朝日小学生新聞の朝小ライブラリー『名作これ読んだ?』のコーナーで本を紹介することになりました。
昨年に引き続き、今年もよろしくお願いします。
こちらのブログでは、新聞の記事内では書ききれなかったあれこれ・補足やこぼれ話などを、つらつらと書き留めていきますので、新聞を読んでいる方もそうでいない方も、気軽にのぞいていってください。
2023年3月読書会『私立・探検家学園1』

3月の読書会のレポートです。
3月の1冊は
『私立・探検家学園1』
(斎藤倫/作 福音館書店)でした。
読書会の様子を少しだけお届けいたします。
※今回も参加者のHさんが読書会の様子をまとめてくれました。
2023年2月読書会レポート『たのしいムーミン一家』

2月の読書会は『たのしいムーミン一家』
(トーベ・ヤンソン/著 山室静/訳 講談社)でした。
今回は読書会に参加している
Hさんのレポートをもとにまとめました!
Hさんありがとうございます☻
『お父さんのラッパばなし』

朝日小学生新聞・朝小ライブラリー『名作これ読んだ?』のコーナーでご紹介した本について、書ききれなかったことをお伝えしたい!と思って、自ら始めたコーナーでしたが、2回ほどさぼってしまいました……反省。新聞の掲載時期とはずれてしまいますが、備忘録として再開したいと思います。
『おはなしばんざい』

9月22日の朝日小学生新聞・朝小ライブラリー『名作これ読んだ?』で『おはなしばんざい』(アーノルド・ローベル/作 三木卓/訳 文化出版局を紹介しました。
新聞のスペースでは書ききれなかったあれこれを書き留めておこうと思いますので、新聞をご覧になれる方はぜひ併せてご覧ください。
『真夜中のパーティー』のこと

7月21日の朝日小学生新聞・朝小ライブラリー『名作これ読んだ?』で『真夜中のパーティー』(フィリパ・ピアス/作 猪熊葉子/訳 岩波書店)を紹介しました。
新聞のスペースでは書ききれなかったあれこれを書き留めておこうと思います。(こちらは大人向けに)
新聞をご覧になれる方はぜひ併せてご覧ください。

